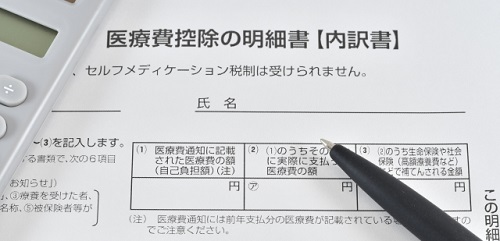よく介護施設の看板に書かれてある『ショートステイ』を指し、その名の通り短く滞在するという施設です。短期入所生活介護というよりもショートステイという呼び方が浸透しているし、その方が通じやすいかと思います。
短期入所して生活する場であり、その目的は日常生活のお世話、支援、機能訓練とともにレクリエーションも取り入れながら行うというものです。
利用者は要介護や要支援の認定を受けた人で、御老人はもちろん障害を持っている人も含まれます。
一人で暮らしているけれど不便が多く、たまには支援を受けながら入浴や食事をするためにショートステイを利用することもあれば、自宅で介護している人が用事などで家に居れない時もしかり、家族といっても介護にも休みが必要ですからショートステイに預ける事もあります。
利用者にも介護者にも良い気分転換になり、孤立化を防ぐこともできます。
利用する条件としても、介護者が冠婚葬祭などの用事で介護ができない時、心身の負担の軽減、利用者の病状や状態が悪い時などが挙げられています。
というのも、支援する目的が可能な限り利用者には自立した生活を送ってもらえるように手助けをするというもで、機能訓練を主としているのです。
施設によってリハビリに力を入れている所もあれば、孤立化を防ぐためにレクリエーションに力を入れて他者との交流で社会性を大切にしている所もあります。
大変便利な施設なのですが要介護、要支援の段階によって一ヶ月に利用できる日数が違い、止むを得ず超過する場合は市町村へ届け出が必要となります。
『短期入所生活介護施設にはベッド数は20床以上が必要』とありますが、高齢化社会となった現在では伴わず、特別老人ホームからショートステイ枠のベッドを設けているのと、利用理由では介護者の休養が多いのが現状です。

短期入所生活介護事業所とは
短期入所生活介護が短期間入所して介護を受ける事で、事業所は簡単に言うとその介護を受ける施設、場所といった意味。「そこ」を指します。
短期入所生活介護事業と言うと、サービス内容を指すことになり、事業者と言うと経営する人を指します。全部を含めて「ショートステイ」という呼び方で通りますね。
そのショートステイをする場所、短期入所生活介護事業所は、介護や支援する人と場所という簡単なものではなく、実に様々な条件をパスして初めて完成します。
先ずは利用者が20人以上ということで、施設内のベッド数は20床以上無くてはなりません。現在の短期入所生活介護事業所の多くは特別老人ホームの中でショートステイ用としてベッドを20床設けている状態です。
利用者一人にかかるベッドの広さ、機能訓練のスペース、食堂も席数によってスペースが必要となり、どの条件も利用者一人一人が十分にサービスを受けられるように作られるのです。
施設は耐火建築物が条件ですが、利用者の生活住居(病室)、静養室、浴室などが設けてある施設は準耐火建築物でも良いなど、細かく指定されています。
病院ではないにしろ、やはり介護の場ですから利用者のプライバシーに配慮した造りも条件に入っていて、面談室は個室かパテーションで区切ることができるようにと考慮されていて、事務所では鍵付きの書庫を設置しなくてはなりません。
そして事業所にはもちろん介護職員が居ます。利用者が3人に対し介護職員は1人以上居なくてはならないなど、そこも時間によって違い、とにかく事業所の設立と共に人員の確保が必要となります。
他にも常勤の必要は無いとされていますが医師、看護師、栄養士、機能訓練指導員も居ます。これらの人材は病院や他の施設からの提携によって配置されるのがが多いようです。
このように人員、施設の設備が整ってから管轄へ申請書類を提出して初めて短期入所生活介護事業所として成り立ちます。

短期入所生活介護と短期入所療養介護
短期入所生活も療養も一般的にショートステイと言われている介護サービスなのですが、この二つの違いは生活の援助(自立への手助け、介護)と、医療的にみてリハビリを兼ねた生活の支援(治療)です。
この二つは似て異なるため、適応する保険も違えば費用も違い、健康保険証があればOKというわけでもなく、40歳になると強制的に加入される介護保険から65歳になると介護保険証明書がもらえます。
自宅で暮らしているけれど短期間介護サービスを受けるためにはどちらを利用するか、それは要支援、要介護の認定を受けてから介護サービスの計画書を作成するためにケアプラン制作事業者か地域包括支援センターで相談をします。
例えば、同じショートステイでも生活介護を退所した日に療養介護に入所した場合は支払いはどうなるのか?単純に介護保険と医療保険が適応されると思われがちですが、ふたつの入所日と退所日や同じ敷地内にある施設かどうかで同日算定ができるかどうかが変わります。
同じ敷地内にある施設では同日算定ができないとか、一つがデイサービスなら同日算定ができるなど複雑です。これらは地域や事業所によっても変わってきますのでケアプランの作成時にしっかりと把握しなくてはなりません。
利用できる日数というのも限られていて、短期入所サービスでは30日まで連続で利用できます。しかし、要介護1の人が療養介護を連日利用する場合は25日間など少し変わってきます。
御家族をはじめ施設の職員の誰もが気付かず利用限度を超えていて自己負担学が膨らんでいた…という事はなさそうですが、大変な時にもう利用日数が少なくなっていて大きく予定が狂う事になり兼ねません。
これも事業所や要介護、要支援によって違うので注意が必要です。

短期入所生活介護 基準費用額と負担限度額
短期入所生活介護を利用する時、利用者は費用の1割と滞在費や食費を支払います。通常の料金で、基準費用学といいます。
料金はお部屋のタイプによって料金も変わって、基準費用額の場合は1日あたりの滞在費でだいたい計2000円から3500円程です。
しかし、所得の低いなど一定の条件を満たす人には費用の負担を軽減するという制度があります。
その目安としては世帯全員が住民税不課税、老齢福祉年金や生活保護受給者、利用者本人の合計所得金額などを参考にしています。
これは利用者負限度額を設定するというもので、利用者またはその御家族が利用者の住民票のある役所の高齢介護課へ申請し、介護保険施設を利用する時に自己負担する額の上限が設定されます。
ここで認定されて『介護保険負担限度額認定証』というものを交付してもらいます。その認定証を利用する短期入所生活介護事業所へ持って行き、支払いがだいたい1000円から2000円程の限度額とどめることができるのです。
この負担限度額の認定は3段階に分かれていて、通常の負担額を支払う(基準費用額を負担する)段階を含めて4段階になり、費用が軽減される段階が1~3段階、基準費用額を負担する段階が4段階、これらを利用者負担額段階といいます。ちなみに4段階の場合は住民税世帯課税の方になります。
この基準費用額を負担する4段階の世帯も一定の条件を満たすと負担額認定を受けることができますが、短期入所生活介護施設の利用は対象外とります。
そして、認定を受けても認定証の有効期限は1年間で、毎年の更新が必要となります。
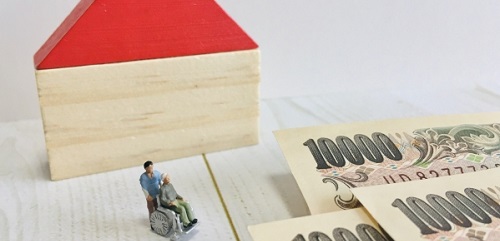
短期入所生活介護事業所と医療費控除
医療費控除とは簡単に言うと医療費を一定の金額以上支払ったら、一定の額の税金が返ってくるというシステム。
通院、入院、薬代だけでなく介護にかかる費用も医療費控除の対象となる場合がありますが、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する際には医療行為があったかどうかによります。
一般的に短期入所生活介護も短期入所療養介護も同じショートステイとして一つに括られがちですが、療養を基準とした短期入所療養介護を利用した場合は控除の対象となります。
短期入所生活介護で食事、排泄、入浴の援助やレクリエーションをして終わったとなると医療行為はないので医療費控除の対象となりません。
しかし短期入所生活介護事業所は運営開始の際に建築物と施設と介護職員の確保だけでなく協力医療機関のと契約書が必要です。
ですから、常勤ではありませんが医師や看護師も居るので利用者が具合が悪くなった際にはそこで医療行為も受けられます。もちろんその費用は対象になります。
他には短期入所生活介護と併せて医療的に見た治療や療養を行った際も対象となります。
例えばリハビリテーション、点滴治療の利用者への対応、生活援助中心型を除く複合型サービスなど色々あり、利用中の様子が分からないにしても事業所は申告に必要な書類を必ず作成してくれます。
その際、報告書にはショートステイ中の様子を記したものの他に医療行為を受けたという領収書などが発行されます。
その領収書をもとに、かかった費用も申告できるのです。医療費控除はとても助かるシステムなのですが、病院や事業所では申告時に必要な書類の作成だけで控除そのものは行えず、確定申告で自分で申請する形になります。