認知症対応型共同生活介護の基準省令とは厚生労働大臣が制定した認知症対応型共同生活介護を運営するにあたり基準を定めたもので、謂わば命令であり、基準が最低限の決まりですから厚生労働省が「最低限、介護職員は◯人で施設の広さは◯◯…」というように決めているもの。
この施設を設立したいとなると、先ずは基準をクリアしてからになります。そして、基準をクリアしていない施設は違反をしている、もしくは例外の基準を設けた施設となるわけです。
ですが、省令は行政の権限で変更ができるので特に介護に関してはよく改正が行われてるのも特徴でしょうか。
まず、認知症対応型共同生活介護の基準は大きく4つに分けられていて人員基準、施設基準、立地基準、運営基準とあります。
人員基準は共同生活を行う場であり認知症症状が比較的軽い利用者が対象なので介護職員の人数は常勤換算利用者3に対し介護職員は一人、夜間は一人以上という基準を設けています。
施設基準は1事業所につきユニットの数は2以下であることや居室は個室で夫婦なら2人でも可などがあります。
立地基準はというと、認知症対応型共同生活介護は地域密着型なので家族や地域との交流が確保されている地域であるとか、市町村によってどの地域に設けるかが違います。
運営基準はどの介護施設もほとんど同じで、各利用者に応じた介護計画書の作成や介護職員へ研修の受講の機会を確保しているかなどがあります。
これは書類上の手続き、介護が安全かつスムーズに行われるための基準です。大きく4つに分けられていても、その内訳は非常に細かく綿密な基準となっています。
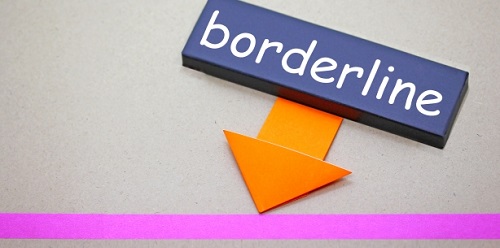
認知症対応型共同生活介護と厚生労働省の関係
認知症対応型生活介護と厚生労働省の関係はというと、認知症対応型生活介護を利用するにあたり要介護認定を受ける、介護保険を使うにしても厚生労働省の管理下で行われています。
ちなみにこれは厚生労働省の介護保険課の仕事ですが、厚生労働省の所在地である霞が関まで足を運ばなくていいのは住民票を置く市町村の窓口が役割を果たしてくれるからなのです。
直接的な接点はないにしろ、介護に携わる全てにおいて厚生労働省の管理下で介護を受けているということです。
認知症対応型共同生活介護施設の基準を省令として出しているのも、また地方自治体の介護事務の指導や介護サービス事業者に対する指導監査を行うのも厚生労働省の介護保険指導室という組織です。
認知症対応型の施設の運営への取り組みは多岐に渡り、その中の一つで認知症地域支援施策推進事業という認知症患者のサポートを実施しています。
全国に認知症地域支援施策推進員を配置し、医療、地域のサポート、介護を繋げます。各地域での情報収集から得た実情に応じてサービスの連携支援、地域の認知症支援体制の構築を実施します。
そこで出来る施設の一つに認知症対応型共同生活介護も含まれているのです。
この施設は地域密着型なので、このような厚生労働省の取り組みがなければ設立の実現もしなければ成り立ちもません。
また、現在取り組んでいるのが認知症対応型共同生活介護はもちろん認知症対応型介護施設数の増加です。
それも厚生労働省の調べにより施設が不足しているとして増加を計画、実施と共に認知症専門の医療や介護サービスの人材の育成にも力を入れています。

認知症対応型共同生活介護の詳細
認知症対応型共同生活介護については、厚生労働省令第34号の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」という項目にまとめられており、その詳細について記されています。
この「厚生労働省令」というのは、公営労働大臣が制定した省令になりますので、省庁関係者はもちろん、「認知症対応型共同生活介護」の関係機関の方もしっかりと内容をチェックしていただきたいと思います。
厚生労働省令第34号では、主に「認知症対応型共同生活介護」について書かれていますが、その構成は、「基本方針」、「人員に関する基準」、「設備に関する基準」、「運営に関する基準」など、複数の項目から成る構成になっています。
そして特に、「人員に関する基準」では、さらに「介護従業者」と「管理者」、「指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者」、「代表者」に関しての詳細が記されています。
また、「施設に関する基準」については、「事業所」、「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」、「居室」、「居間および食堂」、「立地条件について」、「経過措置」という6つの項目から、それぞれの詳細について述べています。
「運営に関する基準」については、まずは「入退去」、そして「サービスの提供の記録」、「利用料などの受領」、「指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針」、「)認知症対応型共同生活介護計画の作成」、「介護など」、「社会生活上の便宜の提供等」、「運営規定」、「勤務体制の確保等」、「協力医療機関など」、「居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止」、「準用」という、都合13の項目から、運営に関する基準について詳細が記されています。
実は、この厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」は、A4の紙面にして実に30ページほどにまとめられた資料であり、関係者、担当者にとってはかなり勉強がたいへんになると思われますが、重要事項ゆえ、しっかりと留意していただきたいと思います。

認知症対応型共同生活介護のアンケート
43特に、介護保険法に基づいた老人福祉サービスに関するさまざま情報を公表している厚生労働省ですが、厚生労働省が発表する情報というのは、そうした老人福祉サービスの利用者だけではなく、サービスの提供者、つまり、介護施設や入居施設、リハビリ施設、病院などにとっても非常に重要な内容を盛り込んだ情報である場合が多いといえます。
むしろ、サービスの利用者よりも、そうしたサービス提供者にとってのほうがより重要性を増す情報も数多く公表されています。
厚生労働省では、そうした情報を作成する際に、より正確な情報を公表するために、適宜アンケートを行ったりしていますが、平成23年度に行われた「認知症対応型共同生活介護に関するアンケート」もそうした意図のもとに行われたと考えられます。
「認知症対応型共同生活介護」というのは、特に、「認知症グループホーム事業者」が提供する介護サービスのひとつです。
「共同生活」というのは、一般的には「グループホーム」と解釈されることが多いため、「認知症グループホーム事業者」と呼ばれる事業形態の事業者は、関連する厚生労働省の発表には敏感に目を光らせておかなければならないといえます。
また、「認知症グループホーム事業者」を対象とした、認知症対応型共同生活介護関連のアンケートも、厚生労働省によって比較的頻繁に行われており、義務ではないものの、認知症グループホーム事業者への積極的な回答を促すケースが多くなっています。
平成23年に行われた「認知症対応型共同生活介護に関するアンケート」もまた、その一連のアンケート調査のうちのひとつです。
関連するアンケートの内容は、やはり「認知症対応型共同生活介護のあり方」についてのものが多く、また、「認知症対応型共同生活介護の施設」に関するアンケートも行われることがあります。
非常に重要な意味を持つアンケートですから、事業者の方はできるだけのご協力おお願いしたいものです。




