生活に困窮した高齢者が行政の計らいで養護老人ホームに入居することになったとき、やはり今後の入居費ですね。困窮していたのですから、費用は誰もが心配することと思います。
しかし、養護老人ホームは行政(市町村)が措置入所という名目で保護したので、費用はその人その人に支払い可能な金額で設定します。
養護老人ホームの費用は、費用徴収基準額として収入や課税額などで、どのくらい支払えるかが階層で分けられています。
無収入で生活保護を受給している高齢者の場合は負担額はゼロの場合もあり、支払い能力に応じた金額となります。
ですが、実際に高齢者一人が暮らすには?養護老人ホームは職員もいて食事や洗濯、生活の介助もしてもらうとなれば?となると、まずゼロでは足りないし、まして費用徴収基準額の中で一番高額な料金でも足りないところなのです。
養護老人ホームの費用徴収と一般に言われる老人ホームとの違いはここで、入居者(扶養義務者も含む)が養護老人ホームに入居するのには「市町村の措置を受けた」からなので、かかる費用は市町村が支払います。
老人ホームは介護保険施設であり、それなりの保険適用と生活費などを支払わなければなりません。
ただ養護老人ホームは入居する前に、入居者(扶養義務者も含む)がかかる費用のうちいくら負担できるかを調査、認定して負担額という費用徴収額を決めるのです。これが費用ですね。
老人ホームとして考えると破格のようにもみえますが、養護老人ホームは措置になるので、このような定額制がとれるのです。
また、支払う費用の認定には収入や課税額だけではなく、医療費や保険といった、支払わなければならない金額も考慮されます。
必要経費といい、調査の段階で申請します。必要経費として認定されれば、収入からその額が控除されて費用徴収額が決まります。
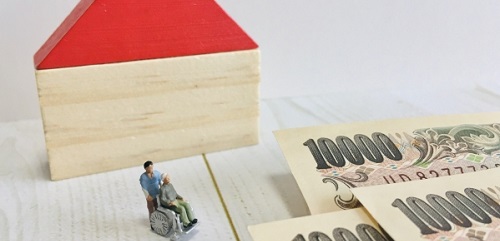
目次
養護老人ホームの費用負担
養護老人ホームは、生活が困窮している高齢者が入居できる施設といいますが、実際にはどのくらい困窮していても入居できるのか?…それは無年金であったり、極端な話ホームレスのような生活になってしまい、住む場所に困った高齢者も入居しています。
とのような状態では養護老人ホームに支払いが可能かとなると、収入や手持ちの資産では不可能という人もいます。
でも入居できているのは費用を支払ったというよりも、行政の措置を受けたからになります。ここが養護老人ホームと生活に困窮する高齢者が入居する接点になるのです。
支払いに困るけれど、全くの無料でもなく、入居者として迎えられたという措置を受ける事に対し支払うのが措置費と言います。
簡単に言えば養護老人ホームにかかる費用でありますが、措置費としてかかる費用のうち前年の収入や課税額を照らし合わせ、措置費のうち本人(入居者)がどのくらい負担して支払うべきかを市町村(行政)が認定します。
住居費、雑費、食費という名目ではなく費用を自己負担する形です。費用負担する金額は費用負担基準額という39階層で割られており、一人一人の支払い能力により金額を認定し、毎月その徴収額を支払うことになります。
養護老人ホームに入居ということは、生活や一人で暮らすには支障が出ているということですから、少なくとも入居する時点では、行政からの保護という措置を受けていることなのです。
養護老人ホームにかかる費用は、施設に支払う費用というより受けた措置に対してかかる費用の中から自分で負担して支払う金額のことを言います。
また、入居している際に個人でかかる交際費や雑費などは必要経費として認められない場合は自己負担として支払います。

養護老人ホームの費用徴収とは
養護老人ホームは老人介護施設ではなく老人福祉施設であり、入居となると行政からの措置となります。
となると、厳密に言えば養護老人ホームに入居した際の費用は措置費となり、入居者または扶養義務者(入居者本人ではない人)が支払うのは措置費のうちの自己負担額になるのです。
この措置費の一部を支払い義務のある人から徴収する事を費用徴収といい、老人福祉施設である養護老人ホームにかかる費用は費用徴収基準額として定められている階層の範囲内で徴収します。
支払う側からすれば費用徴収はあくまで「養護老人ホームの利用料金」といった具合でも、福祉施設なので措置を受けた費用ということです。
この費用徴収基準額は、一人一人の負担能力に応じた額で市町村が認定します。
一般的には経済的に余裕が無い高齢者、身寄りのない高齢者が多く、ほんの僅かな年金などの収入で暮らしていて、このまま一人暮らしを継続するには支障が出るけれど、施設に入るにはお金が無い…という状態の中、行政の措置により養護老人ホームに入居するという流れですね。
なので、その措置により負担する金額を支払う事が「費用徴収基準額」の階層の中から、本人または扶養義務者の収入に応じた額であり、利用料金ではないのです。
費用徴収基準額は、本人からの徴収の場合39階層に分けられていて、扶養義務者からの徴収の場合18段階に分けられています。
分ける目安は納税額、収入、生活保護受給など色々な項目があるうえに現在の支払い能力も考慮してから費用徴収を認定します。
前年は何とか収入を得て納税していたとしても、現在は状況が変わって現状維持がやっとだという場合にも資産状況、家族状況、身体状況などを記入する申込書に明記して提出することで、費用徴収も調節してもらえます。

養護老人ホームの必要経費などの費用徴収
養護老人ホームを利用するのにかかる費用を本人または扶養義務者に請求するのは、そのまま費用徴収といいますが、例えば「養護老人ホームは月に10万円かかるから毎月10万円の費用徴収がくる」とは一概には言えません。
この施設を利用する資格のある人は経済的、家庭環境により一人での生活が困窮した高齢者ですから、その人の課税額や収入額で費用徴収額が各市町村により認定されます。
養護老人ホームは生活保護を受給している人も入居でき、費用徴収額は数段階あるうちの一番低額となっていて、受給額の範囲内の費用徴収基準額が設定されます。
養護老人ホームに入居する人は介護が必要というほどではない高齢者とは言っても、オムツ代はかからないにしろ医療費や雑費などといった必要経費も少なからず発生します。
この場合、生活保護から支給されるには医療費のみとなります。
もちろんそれも前もって現物支給されるのではなく領収書などを提出して請求して振り込みという、あくまで市町村の窓口を通した形になりますが経済的に厳しい高齢者にとって負担軽減したシステムになっています。
養護老人ホームに入居した際、「必要経費を支払う」というよりも、前年の収入や納税額などで認定された費用徴収基準額そのものの中に含まれているのです。
また、養護老人ホーム側も生活保護に対応したケアを組むので、受給額を超える費用徴収が来ることはありません。
生活保護を受給している扶養義務者が支払う場合でも同じく、費用徴収は必要経費も含めて負担能力に応じた額を徴収するよう定められています。
そこで、入居者が通院をして医療費がかかった時には扶養義務者が市町村へ必要経費として請求すればかかった医療費は受給してもらえます。
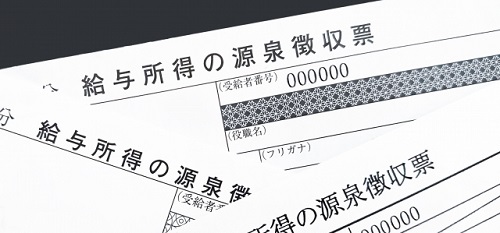
養護老人ホームの費用徴収基準
養護老人ホームにかかる費用は、利用料金や住居費というよりも行政がとる措置なので措置費となり、その措置費のうちの一部を自己負担する金額が、支払うべき費用になります。
この自己負担する措置費のうちの一部は、支払い能力や課税額、収入により市町村が認定して決めるのですが、それが費用徴収基準という基準額が定められていて、さらに39階層に分けられています。
大まかに、養護老人ホームの支払い金額が39段階あるという見方をすると簡単でしょうか。
費用徴収基準は、経済的、環境、身体などに支障が出て、介護が必要とまでないかないけれど一人暮らしをするのには困難となった高齢者が入居できる施設なので、支払い能力を考慮して諸々を含む金額が費用徴収額となっています。
しかし、養護老人ホームに入居している最中に病院にかかって医療費が発生したり、もともと抱えていた止むを得ない金銭問題への返済、または配偶者への仕送りなど、人が生きるうえで実に様々な出費があります。
これは必要経費といい、費用徴収額の認定をするのに不利になります。
課税額や収入だけで徴収額を決めては、以後養護老人ホームへの支払いにも支障を出しかねません。この必要経費は、出費に対し控除という措置をとり、その上で徴収額を認定します。
ただ、必要経費として市町村が認めた場合のみ控除(出費により支払うべき税金が安くなる制度、養護老人ホームを利用する場合には、出費を含み、費用徴収を行ってもらうための制度)が受けられるので、領収書の提示など細かい申請が必要になります。
費用徴収基準を認定するには収入や課税額、財産状況だけでなく出費に関しても申請が必要になるのです。
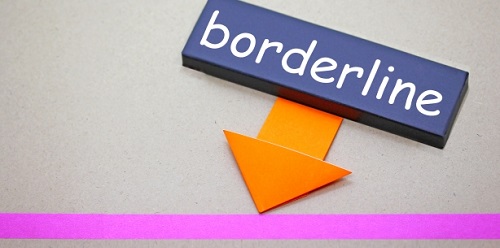
養護老人ホームの月額費用徴収
養護老人ホームは経済的に困窮した高齢者が入居するものとし、安く入居できるという認識で、費用は月に8~10万円とは言われますが、この情報もあながち間違いではないのです。
この金額は、入居者が支払う費用徴収基準額の一環であり、その中で高額な階層区分の金額なのです。
では、経済的に困窮した高齢者にとって毎月8~10万円支払えるかというと、全員支払えるものではないし、何より養護老人ホームは様々な状況で入居してきた人がいるので支払う金額はほぼ一人一人違います。
支払う費用は、支払うのが本人の場合は39階層、別の人が支払う義務を持つ扶養義務者の場合は18階層あります。
この費用徴収額は老人福祉法により定められ、支払う人の前年の収入や課税額で認定し、その額が、その年の毎月かかる費用として徴収されます。
ですから「月に◯万円…」といった、まるで月額かのような情報がキャッチされるのでしょう。本来は月額というよりも、年間を通して1ヶ月◯万円負担するというのが正しいはずなのです。
しかし、前年の収入云々を別として例外もあり、扶養義務者が別の件で福祉施設に支払いをした場合や通院で医療費など必要経費がかさんだ際には市町村へ申請して費用徴収基準の階層の変更を検討してもらうこともできます。
これには領収書など証明となる物が必要になりますが認められた場合、翌月から費用徴収額が変更してもらう事が可能です。
ただ、この費用徴収額の階層の変更はあくまで例外措置なので、返還など他の措置で対応する事もあるようです。
また、入居者が入院した際、翌月の徴収では入院したその日から日割りで差し引いた額が徴収されるといった対応もあります。

養護老人ホームでの扶養義務者の費用
養護老人ホームの費用を支払うのは入所する本人か、扶養義務者のいずれかです。
扶養義務者場合、入所者本人と同居していた子、または配偶者となりますが、入所者本人が一人暮らしであっても扶養実態があったなら、その扶養していた人が費用を負担することになります。
本人が支払うケースとは少し違い、扶養義務者が前年に支払った所得税額に基づき費用徴収を行います。
そして入居者本人が費用(措置費)を払えたとしても、措置費に満たない額しか徴収できなかった場合は扶養義務者からその差額を徴収することになります。
一見厳しいようにもみえますが、徴収限度額という制度も設けられているので、血縁はあるものの疎遠だった血縁者にまで急に徴収がいくことがなく、扶養義務者として見做すにも範囲を定めています。
この制度は、何か事情を抱えて一人暮らしをしている、または御家族とは随分長く疎遠になっているなどの養護老人ホームへの入居する人の現状に伴い、定められていているのです。
実際に扶養義務者として措置費を支払う人は、事情があって本人(入居者)とは住めないというような続柄です。代わりに負担する額も支払い可能な範囲内としています。
このように扶養義務者が負担する制度も、入居者本人の経済的困窮や家庭内の事情、現在に至るまでの経緯を考慮して対応できるようになっています。
養護老人ホームへの入居者の生活が不安定さが大きく反映されている点でもありますが、扶養義務者が死亡、または措置費を支払う事が出来なくなった際には市町村の窓口に扶養義務者変更届けを提出し、新たに扶養義務者を立てなければなりません一人扶養義務者の責任が消失した時点で措置費を支払う人が居なくなった場合は、生活保護を申請して措置費を支払うこととなります。

養護老人ホームの費用と法律
養護老人ホームの利用者への費用を徴収するにあたり、老人福祉法の規定に基づき市長が利用者本人または支払い義務のある納入義務者(扶養義務者)へ通知します。
この通知に記された額が、本人の支払い能力、または扶養義務者の課税額によって認定されます。市長から額の認定通知が来ても、その認定通知に記された額は老人福祉法により決めた額なのです。
そのため、入居費用は一人一人違いますが養護老人ホームという生活に困窮している高齢者の施設であるため、平等とも言えるシステムです。
養護老人ホームの費用に関する老人福祉法では、支払い金額が1段階から39段階に分けてあり、この段階は対象収入による階層区分を表していて、対象収入というのが前年の収入から保険料など必要経費を控除した後の収入を指します。
老人福祉法では、対象収入をみて費用(費用徴収基準額)を決めます。この費用の支払いが本人ではなく扶養義務者の場合、対象収入とは言わず税額等によるものとし、18段階あって一番低額な段階で生活保護受給者からはじまり、一番高額徴収とされる段階では前年の納税額が627001円以上~という階層区分に分けられています。
18段階のうち、1~4段階までは生活保護法による被保護者や市町村民税などの非課税の区分となり徴収基準額も低額になっています。
なお、老人福祉法では扶養義務者が他の社会福祉施設への扶養義務者となっている場合には徴収額の一部から全額が免除されるという規定も設けています。
よって、扶養するにあたり徴収基準額がかさむことが無いよう定められています養護老人ホームは低額と言われるのも、このように利用者本人や扶養義務者の生活環境に基づいて老人福祉法で決められているからなのです。






