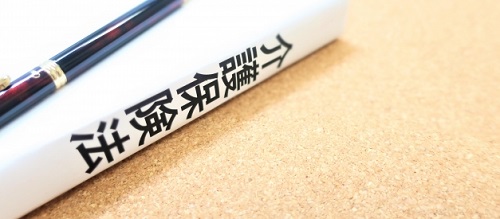老人福祉施設である養護老人ホームは、身体的、経済的、環境的な理由で生活が困難になった65歳以上の人が入居する施設です。
生活が困難になったのには、この三つ全てではないにしろ65歳以上という高齢を考えると困窮した生活を改善させるのは非常に困難となります。
例えば、お金を貯めてもっと良い所に住もうにも、仕事を増やすのは体力的に適わないのです。そこを市町村(行政)が生活に困っている高齢者を保護する措置をとるのに、養護老人ホームへの入居があります。
養護老人ホームには衣食住が確保されており、そこへ入居措置を受けた高齢者は自立の援助を受けながら生活します。
この施設の役割は「自立のため」ではありますが、実際には人間らしい生活を送る事を目的とした所で、介護が必要になるなどして入居対象外となるまで長く暮らす人も多いのです。
もちろん、中には養護老人ホームに入居してから家族との関係が改善し、自宅へ戻り生活するようになったとか、状況が変わって遠方に住む子供の家で住むことになり退去した高齢者もいますが、多くの入居者は最終的な自立には当てはまらないのが現実です。
ただ、生活の確保が大きな役割ですから自立は二の次として問題はないとの事です。
高齢者施設なだけに職員も最低限ですが配置されており、日常生活を送るための機能の回復、減退予防に機能訓練をしたり健康管理を行っています。
養護老人ホームは単に住む場所の提供ではなく、介護が必要では無いものの、保護が必要という高齢者にとって充分に機能も役割も果たしています。

養護老人ホームの入所基準
いかなる老人施設も市町村によって違いがありますが、一般的には65歳以上が入所基準年齢で65歳未満は対象外になります。
養護老人ホームも入所対象者は65歳以上です。しかし60歳以上でも一定の基準を満たしていれば入所できることもあります。
これは年齢という条件とは別の、『65歳以上の人で身体上、精神状態、経済上、環境上の理由で住居において生活できない』という入所基準のうち『65歳以上』の条件を省いた基準です。
さらに60歳未満でも衰退が著しく保護や措置を受ける対象でありながらも該当する施設に空きがないなどの理由で措置入所できる場合もあります。これは厚生労働省の老人福祉局により定められています。
この入所基準、養護老人ホームへ入所する老人への介護は基準としていなく支援を目的とし、入所基準である『身体上の理由』という点では「一人で生活が困難になった場合」といっても、一人で入浴や排泄ができないなど介護が必要となる要介護認定を受けていれば入所はできません。
あくまで一人暮らしは不安という状況です。(介護認定を申請していなくとも第三者から見ても要介護度数が高ければ入所は不可能)とはいえ、市町村や施設によってこの要介護認定の介護度数にもよりますが、介護度1であれば入所可能とするところもあるので一概には言えません。
中には入所時に介護度1だったけれど、生活をするうちに介護度数が上がってもそのまま入所続行するケースもあります。
介護度が上がっても、他に移るべき施設に空きが無く、なんとかそこで生活ができるなら…という「やむを得ない状態」に該当し、厚生労働省はそのような条件下にある高齢者への自立、支援を目的としています。

養護老人ホームは自立の人も入所可能か
自立した人は養護老人ホームへ入所できるのか?というと、できます。養護老人ホームの入所基準は、65歳以上の高齢者で経済的、身体的、家庭環境の理由から自宅で生活ができなくなった人。
身体的というのは元気である事が基準であり、元気だけど一人で生活をするには不安という程度の状態が基準となります。つまり、養護老人ホームの入所基準の「身体的に」という点では自立した人を指しています。
自立とは要支援、要介護認定を受けていない人。入所基準では自立した人が対象なのですが、実際には要支援認定を受けていても入所可能な例が多いのですし、中には要介護認定を受けた人も入所している施設もあります。
そして、養護老人ホームの入所基準では要支援者も含まれています。
ここが一般的にいう身体的な自立と入所基準対象の違いなのですが、要するに支援が必要でも生活に困らないぐらいの状態とみていただいた方が良いでしょう。
養護老人ホームは介護保険施設ではなく老人福祉施設で、目的としては自立支援ですから身体的に自立した人は経済的、環境的に生活が困難になったという基準を満たせば入所対象なのです。
(経済的、環境的に自立していて身体的に自立していない人は介護保険施設の利用となるわけです)
施設にもよりますが、一通り自分で出来る範囲内でも食事や入浴といった日常生活を送るにあたりお世話をしたりレクリエーション、生活向上サービスを受けられます。
これらも自立した人が対象であり、トイレの使用や入浴設備に不便が出てくるなど、これ以上のサービスが必要となってくると退所して他の施設へ移るなどの措置を受けることになります。

厚生労働省による養護老人ホームとは
様々な理由で生活に困窮する高齢者に、自立する支援をしながら生活してもらう所が養護老人ホームですが、介護の場ではなく保護という行政が行う措置です。
よって介護施設ではなく福祉施設であり、養護老人ホームを運営するための基準は老人福祉法により定められています。
本人へ養護老人ホームへの入居を認定するのも行政であり、本人の住民票が置かれる市町村の仕事ではありますが、その仕事を割り振ったり、当の養護老人ホームの基準を定めているのも上を辿れば厚生労働省に繋がります。
例えば、市町村の窓口で「養護老人ホームに入居資格のある…」、「養護老人ホームの費用徴収基準額」といった正式な数字や詳しい条件などの記述は皆、厚生労働省老健局長通知と記されています。
これは老人福祉施設は厚生労働省の老健局という部署が担当しているからです。
また、養護老人ホームだけでなく介護の場や福祉の場などの基準の改正も厚生労働省が統計をとってニーズに答えるべく改善を図るために行っています。
養護老人ホームも介護に関して改正が有りましたが、これも全国の市町村へ直接調査をして取り決めたものです。ちなみに、改正というのも厚生労働省が取り決めた老人福祉法が元となっています。
厚生労働省とは社会福祉、社会保障、公衆衛生と、労働に関する行政機関であり、私達住民からすると市町村の窓口の、さらにその窓口といったところです。
養護老人ホームはもちろん、高齢者施設ととても深い関わりを持つ厚生労働省は、様々な形で直接的なサポートに繋がるべく日々、高齢者だけでなく全ての国民の向上を目指している機関です。

養護老人ホームの介護保険サービスを利用
養護老人ホームは介護保険施設ではなく、ひと通り自分で身の回りの事はできるものの自宅で一人での生活が困難になった人が対象です。
身体や精神に障害があったり、経済的、環境的に一人暮らしができなくなった65歳以上の人が入所資格を持ちます。そのため養護老人ホームの職員は、介護ではなくお世話をする形になります。
しかし入所後に介護が必要になった場合は介護保険を利用して外部保険サービスを受ける事か可能な施設あったり、2006年の改正後には外部サービス利用型特定施設生活介護の指定となりました。
安全に入浴する事かできる介護施設へ週に数回通うなど、施設の設備に応じて入所時に介護支援相談員に依頼してケアプランを作成したり外部サービス利用型の施設へ入所するなど、あらかじめ設定するケースがほとんどです。
または途中、介護が必要になった際には施設の設備や固有しているサービスや受け入れ体制により利用できる介護サービスが決まってくるので様々です。
そこで、介護を受けるための介護保険ですが、養護老人ホームは介護保険施設ではないので介護保険サービスを利用するにあたり少し複雑になります。
養護老人ホームは市町村がとる措置となり、介護保険を利用してかかった費用は利用者負担の一部として加算します。
つまり自己負担額が発生するということで、そこを養護老人ホームの目的である措置に伴い、市町村が自己負担額を助成するという形になります。
養護老人ホーム利用助成金支給申請書と領収書、支払金口座振込依頼書を市町村へ提出します。
養護老人ホームと介護保険サービスの利用、より安全に健康に生活するために改正がされてはいますが実際には入居者の状態からすると、ほぼ介護予防のサービスを利用するケースが多いようです。
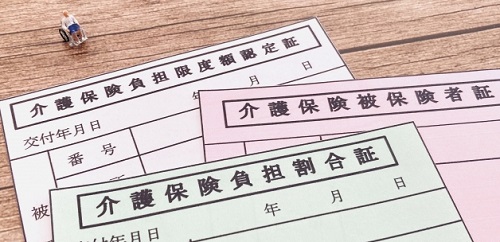
養護老人ホームと介護保険法の関係
介護保険法は介護保険制度を設け、高齢者や障害者の生活や健康をサポートするための法律でありますが、養護老人ホームとの関係はさほど深くありません。
要介護や要支援の認定を受けて介護サービスを利用する際に、サービスにかかる費用の全てを負担せず一部の負担で済むようにと掛けてある保険が介護保険なのですが、養護老人ホームは要介護や要支援の認定を受けていると入居の対象とはなりません。
養護老人ホームは老人福祉法により制度を設けられた老人福祉施設になります。介護サービスを受ける施設は介護保険施設です。
しかし、養護老人ホームで生活するうち、介護が必要となった場合、または自力である程度生活できるるものの浴室など介護仕様の設備を利用したいといった時には介護サービスが必要となったら、老人福祉施設に入居しているのでその介護費用を全額負担になるかというと、そうではありません。
その場合、老人福祉法に基づき設置された老人福祉施設は介護保険が適用されるのです。
養護老人ホームに入居している人の場合、介護は外部サービスを利用となるので、その時にかかった食費が自己負担になります。
養護老人ホーム入居の対象ともなる「経済的理由で一人暮らしが困難になった」ということから、負担額軽減という措置があります。
養護老人ホームと介護保険法の一番密接な関係というのが、措置をいかに有効活用するかといった点でしょう。
ある程度自力で生活できるものの、入居後に設備の整った浴室や機能訓練室を使用したいなど、状態の変化に対応するために介護保険適用となるサービスを併用できれば、介護が必要になったから退所して他の施設へ行かなければならないということも少なくなるというわけです。