有料老人ホームは民間事業なのですが、厚生労働省が定めた老人福祉法において人員、設備整備、運営基準を満たさなければ運営されません。
有料老人ホームは介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームとあり、これら三つの有料老人ホームはサービスや入所する目的、設備などが違います。
施設や地域によっても違いが出てきますが、基準(平均的な水準)は似ています。
介護付の場合は個室一部屋につき実有面積は18m2以上、一人当たりの床面積が13m2以上で住宅型の場合も同じで個室一部屋につき18m2以上、一人当たりの床面積が13m2以上です。健康型の場合は全国的な同一基準はありません。
共通するものは、一人一人が快適に過ごすのに必要な広さを取り、その施設に入所した目的に見合った設備が整えられているということです。この基準を基に、費用や利用者のニーズ、予算に合った様々な施設が設立されます。
例えば、個室がとても広い介護付高級有料老人ホームを造るとなると最低限の実有面積が18m2以上であれば良いということになります。
5反対に、低料金でできるだけコンパクトな造りにしたいとなっても同じ面積を取り、下回らないよう設計して設備を整えることが必要となります。
そこへプラス、車椅子での移動に差し支えない広さの廊下や一時介護室の造りなども細かく規定があります。全てプライバシーと介護と安全な生活の空間を確保するための最低限必要な設備です。
健康型は、施設によっては軽度の要介護なら入所可能という所もあるので、施設内の面積に関しては若干の違いが出てきますが、どこも快適に過ごすための広さは確保されています。
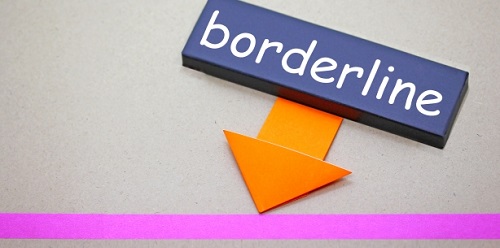
有料老人ホームの建築基準法
有料老人ホームは大きく分けて介護付(ケア付)、住宅型、健康型と3種類あり、その中の健康型有料老人ホームは老人福祉法による詳しい基準はなく、入所した利用者が契約に沿った快適な生活を続けていくための設備が整っていれば問題はないとされています。
ですが、介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームは様々な基準があります。
その有料老人ホームとなるのに建設基準法というものが設けられ、先ずは基盤である構造が利用者が快適に安全に過ごせる設備を有し、耐火建築物または準耐火建築物であり避難設備、消化設備、警報装置が充分であることが前提となります。
そこから介護付有料老人ホームは介護居室を設け、住宅型有料老人ホームは一般居室を設けます。いずれも基準の面積は同じで、一時介護室という居室もなくてはなりません。
これは介護付でも住宅型でも介護を受けられる施設なので必要で、住宅型有料老人ホームでは機能訓練室と医務室(健康管理室)がない形になります。
介護付と称していなくても住宅型有料老人ホームも色んな施設があるので、看護職員室を設ける施設もあります。
要介護度が高い人も受け入れられる住宅型有料老人ホームですね。また、住宅型にはレクリエーションやスポーツ施設はありません。これは介護付のみ設けられる「健康・生きがい施設」というものです。
これらの基準を満たしていない設計では有料老人ホームに該当せず、用途としては寄宿舎か共同住居となります。基準を満たした設備を整えてから、初めて事業開発届けを県知事宛に提出します。
また、有料老人ホーム設立に、既存の建築物を改修する場合は用途の変更確認をして建築物基準法に基づき改修しなければなりません。
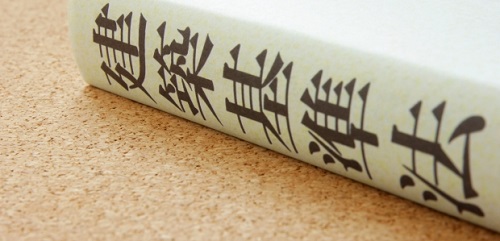
有料老人ホームの設置運営標準指導指針とは
有料老人ホームとは介護付、住宅型、健康型と大きく分けて三つありますが、内容は施設により違いを見せていて一律の規則やサービスに馴染まない面もあります。そこを纏めるのが設置運営標準指導指針です。
有料老人ホームは事業者と利用者が直接契約することが多いため、契約の履行や締結に必要な情報が利用者へ提供されているかが重要となります。
例えば介護付といっても外部サービスで介護を受ける訪問型の場合には、その施設で生活するにあたり入居してから不具合が生じた時に初めて「このサービスは実施されない」と知る事がないように情報の提供を徹底したり、支払った入居金を考慮してサービス水準を下げないよう努めるため厚生労働省にかわり行政が行う指導です。
直接的な生活、介護の面だけでなく老人ホームの定義の周知といった事業者への指導や老人ホームに該当することの判断、有料老人ホームの届出の徹底や特定も実施しています。
この意図はやはり、一定の基準を満たしていれば有料老人ホームの開業ができるという事実の上で成り立つ施設の取り締まりといったところで、届出がされていないホームには老人福祉法に基づいた命令や罰則の可能となり、有料老人ホームの運営や維持のために事業者に対しても入居者に対してもなくてはならない指導なのです。
ある程度の基準を満たしていても廊下の幅など何らかの基準を満たしていないため届出が行われていない施設も有りますが、指導指針に適合されていなくても届出義務があるので、そういった都道府県を把握していない、所謂もぐりの施設にも届出を促すことができます。





