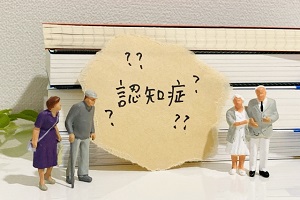認知症対応型共同生活介護は、その名の通り認知症の人が共同生活を送りつつ介護を受ける場所(施設、事業所)です。認知症でも介護保険の適用ですので65歳以上の認知症症状のある人が利用できるというものです。
その目的とは、入浴、食事、排泄など生活の介護や補助を認知症専門の介護職員から受け、可能な限りの自立を目指しながら共同生活の中で認知症症状の緩和、悪化の予防です。
そして、その施設は(認知症以外の)疾病や怪我で共同生活が困難にならない限りは利用者にとって生活の拠点となります。高齢者の生活の拠点ということは終末期ケアや臨終時の対応もしています。
また、認知症対応型共同生活介護は設立時に協力医療機関を定めていますが、基本的には医療ニーズを必要としない介護施設です。
しかし、医療連携体制を整えている施設もあり、訪問看護サービスを受けることができ主治医との連絡調整をスムーズに運ぶことができるし、インスリン注射やカテーテルを要する利用者にとっても安心して生活ができます。
認知症対応型共同生活介護を利用するにあたり、かかる費用を大きく分けると介護報酬、その他のサービス加算、これらを介護サービス料といい、利用者は一割を負担します。あとは生活費です。
生活費は自費で衣食住全てで食費、居住費、理容費、オムツ代になりますが比較的安い介護施設にあたります。この認知症対応型共同生活介護は地域密着型の施設で、その市町村の住民票を持った人しか利用できません。
しかし、それでも定員が埋まりやすく待機している人も多いのが現状です。厚生労働省は認知症対応型共同生活介護を増やす計画を立て、実行しています。

認知症対応型共同生活介護での重要事項説明書とは?
重要事項説明書は「そちらの認知症対応型共同生活介護に入所します」という契約する前に、説明を文章で記された書類です。
これは介護認定を受け、利用する介護サービスをケアマネージャーの相談して認知症対応型共同生活介護へ入所ということになり、その際に利用者またはご家族がサービスを選択するために必要な重要な説明を事業所から利用者またはご家族へ行うもので、最終的に入所すると決めなかったとしても、「重要事項説明書として受け取り、読んで説明を受けました」という証明になります。
説明の内容は施設の全てで、事業者の名称、施設長、電話、ファクス番号から始まり、サービス内容はもちろん人員、建築物の詳細、基本サービス料や加算内容も含みます。提携している医療機関、消防署、苦情相談窓口もありますし、もしも入所した際にかかる費用の目安も記されています。この重要事項説明書の最後の欄には説明を文章でうけたという署名が必要になります。
施設によって重要事項説明書は違い、その違いは費用の目安(見積もり)の欄がなかったり、最後は署名だけでなく捺印も必要なタイプもありますが、あくまで認知症対応型共同生活介護の介護保険法の基準に基づき運営している施設なので、記載事項が多いか少ないかの差です。
この重要事項説明書を読み、説明を受けたと証明しなければ入所の契約ができません。
しかし、細かく記載されているけれど質問などはその都度でなければ出てこないのが現状です。有って無いような物かもしれませんが、入所の契約の前の大切な過程なのです。

認知症対応型共同生活介護のグループホームとは?
グループホームとは認知症にかかった高齢者が1ユニット(5~9名)ごとに共同生活をする介護施設です。
グループが仲間、集団といった複数人を表すので、そのグループにホームが付いて「共同生活」となります。
介護業界ではグループホームというと共同生活介護を指し、さらにグループホームを利用できる人の対象が65歳以上で認知症の要支援2から要介護5までの人になります。
ですからグループホームは、高齢の認知症の人が生活しながら専門の知識を持つ介護職員から介護を受ける「認知症対応型共同生活介護」という事業所です。
正式な名前が認知症対応型共同生活介護ですが、グループホームでも充分に通じます。単に高齢者が共同生活介護を受ける事業所はグループハウス(特別養護老人ホームなど)なので、グループホーム=認知症対応型共同生活介護ということです。
対象となるのは要介護5までとは言いましたが、実際には認知症対応型グループホームへ入所できる人は要介護2までのいうのが現状です。
というのも、グループホームの特徴は自立支援なので、ある程度は身の回りの事が行えて、共同生活ができる状態の人が対象だからです。
共同生活とはいえ基本的には個室です。ご夫婦で相部屋を使ったり、または希望により相部屋ということも可能です。
個室、希望に沿った部屋体制はプライバシー重視のためで、機能訓練、活動や食事などは他の利用者と共に行います。
そうすることで認知症の進行を抑える事ができ、認知症症状の緩和にもつながります。
グループホームという小規模な生活空間の中、認知症専門の介護職員から認知症症状である不安や妄想などの周辺症状への対応も速やかに行ってもらえます。

認知症対応型共同生活介護で使える訪問看護サービス
認知症対応型共同生活介護施設には医療連携体制を整えている施設もあります。施設側は行政や各都道府県の看護ステーション協議会といった団体に相談して契約する看護ステーションを決めて委託契約を結びます。
利用者がここで使えるサービスが週に一度以上の訪問看護です。サービス内容は利用者の日常的な健康管理、利用者の症状悪化時の医療機関との連携や調整、看取りへの対応強化です。
認知症対応型共同生活介護は共同で生活する場であり、ある程度は自力で生活ができる事が入所の条件であって症状の悪化や他の病気や怪我で入院が必要になると退所する形になるので、訪問看護により入院回避や早期退院ができる事、インスリン注射やカテーテルが必要といった医療依存度の高い利用者受入ができる事、疾病の早期発見などメリットがたくさんあります。
そういった施設は医療連携体制加算というものが加算されます。加算する条件としては看護師の配置と24時間の連絡体制の確保、重度化・終末期対応指針・家族の同意です。
(ちなみに、看護師でなくてはならず准看護師では本加算は認められず、さらに看護師の事業所での勤務実態のないオンコール体制では加算は算定されません。)
それらの基準をクリアして利用者へ医療連携体制加算を算定できる体制を作ります。そしてその施設で利用者はケアプランに添った看護を受け、介護報酬とその他の加算も含めて医療連携体制加算の39単位も支払うことになります。
この訪問看護の介護報酬の支払いは、医療保険の適用か介護保険の適用かは利用者の病名や回数によって違います。