養護老人ホームは生活に困窮した高齢者のための福祉施設で、ルーツは明治時代に設立された慈悲活動家による養老院です。
しかしその後、長きに渡り国のサポートは受けられないまま慈悲目的で運営されており、1929年にやっと生活を扶助する施設へと変わりました。
さらに1963年(昭和38年)には老人福祉法が制定され、養護老人ホームという名称に変わり、設備及び運営に関する基準を厚生省が取り決めました。
しかし、現在は養護老人ホームのみならず福祉施設や介護施設などの設備及び運営に関する基準をみると「厚生省」ではなく「厚生労働省」と記載されています。
これは2001年に厚生省と労働省が統合されたためです。養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を制定した当時、厚生省が医療、保険、社会保障を所管していました。
そこへ2001年に労働問題を担当する行政事務などを行う労働省も統合されたのです。
設備及び運営に関する基準とは、まさに施設の土地から安全の確保や健康的な生活を目的とし、設備、職員数と職員配置、協力病院の確保というように、実に多くの基準を満たさなければなりません。
これらの基準を設ける目的は、老人福祉法により定められた基準である第一章の『総則』に記されています。
入居する高齢者に心身共に健康で安全な生活の確保に努めなければならない事を前提に、高齢者を取り巻く環境を整えるためです。
この老人福祉法をもとに、入居するべき施設をピックアップし、その施設の設備及び運営に関する基準に伴い、入居者は生活を、職員は然るべき措置を施します。
設備及び運営に関する基準は、謂わばその施設ごとの規律であり、それがなければ運営はおろか入居者は健康的な生活を送ることができません。
厚生労働省は、円滑な福祉を行うためにも基準を制定し、時には改正をして入居者、職員、市町村のニーズに答えるよう努めています。
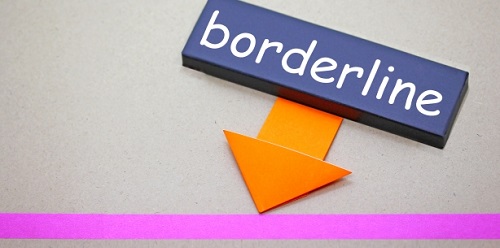
条例と養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
養護老人ホームには設備や職員配置、料金、入居者への対応などほとんど全てが基準という決まりで定められています。
しかし、基準に伴い運営するとはありますが、実際に現場(養護老人ホーム)では基準をクリアしていない事もあります。
これは基準から外れて運営していて違反かというとそうでもなく、基準に伴い定められた条例を基に運営しているのです。
養護老人ホームのように市町村が運営する福祉施設は基準や政令を基に、地方の公共事務や行政が独自の法規を制定し、条例として定めて、改めてその市町村の養護老人ホームの決まりとして設けた規律ともいえます。
基準として定められているものを、直接関係のある市町村が入ってから「本来(基準としては)養護老人ホームは◯名入居させなくてはならないけれど、人工的にも◯名確保は難しいから△名以上とする」など条例を作ります。
この条例もしっかりと行政事務などの会議の決議を経て決定しますが、条例を作ることができるだけに改正が多いのも特徴です。
それでも、条例として施設と直接関係のある市町村の独自の規律を持たなければ運営が難しいところなのです。
ざっくりと、「養護老人ホームは入居資格は介護が必要でないけれど生活が困難な65歳以上の高齢者で…」というような、基本的な決まりは少し調べると知ることができます。
しかし、いざ入居となるとその入居資格から外れていても住民票をおく市町村によっては入居が可能ということがあるのです。
それが、基準では入居は不可能だけれど、その市町村の条例では入居可能というものになるのです。
条例とは、少し決められたルールを変えたけれども、変えてからのルールを守れば運営しやすくなるから作った基準ともいえます。

養護老人ホームでの健康診断に関する基準
養護老人ホームは運営にあたり、様々な「基準」という条例が有ります。施設の設備や職員の配置はもちろん入居者への基準も定められています。
その中の一つに健康診断があり、これは入居前と入居後には年に2回実施されます。入居者の健康の確保だけでなく、設備や職員が対応できる範囲内でないと養護老人ホームでの安全な生活が続行できないからです。
入居前の健康診断は大きな病気がないか、結核など感染症がないか、病歴や現在の健康状態の把握というように、継続的な医療管理が必要であれば入居対象外となりますので、ほぼ入居審査の一環のようなものです。
施設によっては要介護度1だったり、認知症症状があっても入居できる所もありますが基本的には対象外になります。
入居後の健康診断では健康管理が大きな目的であり、これは設備及び運営に関する基準の「健康管理」という項目で定められていて、運営の基準にも「入居者の健康管理に努めなくてはならない」と記されています。
協力病院としてあらかじめ指定している医療機関の協力のもと必要に応じた健康維持の適切な処置と記されています。
特に検査の内容は細かく記載はありませんが、血液検査や尿検査、心電図検査を実施していて、大抵の施設では胸部レントゲンを含むようです。
養護老人ホームでの医療サービスは最低限しか受けられないので、大きな病気があれば施設内での「健康維持の適切な処置」は対応しきれず、「入居者の健康管理に努めなくてはならない」という基準から外れてしまいます。
設備及び運営の基準で定められた設備と職員の配置は、あくまで健康な65歳以上の人が介助を受けながら生活することが前提で設けられているのです。






